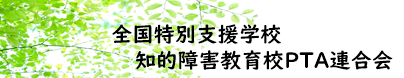- トップページ
- 全知P連紹介:会長挨拶
会長挨拶
ご挨拶
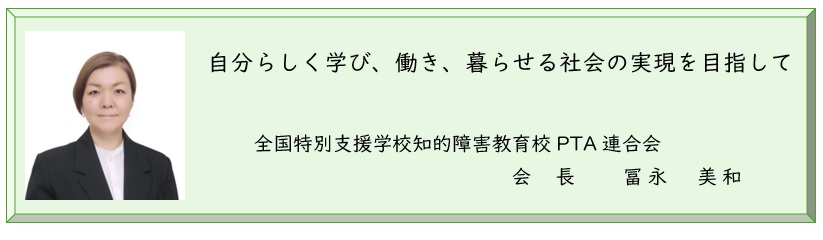
全国特別支援学校知的障害教育校PTA連合会(全知P連)のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
令和7年度、全国の知的障害教育校PTAの皆さまと共に歩む機会をいただきました、都立田無特別支援学校PTA会長の冨永美和と申します。昨年度に続き、子供たちの笑顔と安心・安全な未来のために、そして子どもたちの代弁者として、一人ひとりの声を社会へつなげていけるよう、微力ながら力を尽くしてまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。
私は、知的障害と自閉スペクトラム症がある息子の母です。現在、息子は高等部1年生となり、家族で落ち着いた日々を過ごしておりますが、ここまでの道のりは決して平坦ではありませんでした。
さまざまな“壁”にぶつかりながら、なんとかここまでたどり着いた─それが率直な実感です。
最初に立ちはだかったのは、「障害受容の壁」でした。息子の特性をどう理解すればいいのか分からず、戸惑いと不安の連続で、外出先で床に寝転び泣き叫ぶ息子の姿に、周囲の視線が突き刺さるように感じたこともありました。何が嫌なのか、どうすればパニックを防げるのか、分からないことばかりでした。
しかし、絵カードやマカトン法などの視覚支援を取り入れることで、少しずつコミュニケーションの糸口が見え始めました。息子との信頼関係が少しずつ築かれ、拙いながらも言葉でのやり取りができるようになったときの喜びは、今も忘れられません。
次に訪れたのは、「思春期の壁」です。中学3年の冬、息子は突然、人の視線を極端に怖がるようになり、外出が困難になりました。大好きだった学校にも通えなくなり、不安定な日々が続きました。親としてどう支えたらいいのか分からず、家族も心身ともに疲弊していきました。そんな私たちを支えてくれたのは、学校の先生方、福祉の専門職の皆さま、そしてPTA活動を通じて出会った友人との対話でした。
「家族だけでは抱えきれないこともある」と改めて気づくとともに、「支え合えるつながりがあれば、乗り越えられることもある」と実感した経験でした。
そして今、私たちが社会全体で向き合っているのが、「インクルーシブ教育実現の壁」です。特別支援学校や支援学級に在籍する子どもたちと、通常の学級に在籍する子どもたちが「交流及び共同学習」として関わる機会が設けられることもありますが、それは多くの場合“イベント的”なもので、日常的な接点や自然な交流が十分にあるとは言えません。理想は、子どもたちが日々の生活の中で自然に関わり合い、互いの違いを知り、理解し、認め合いながら共に育つこと。そこから得られる学びは、教科書以上に大きな価値を持つと信じています。この実現のためには、制度の柔軟な運用、自治体や教育委員会の理解と支援であり、次期学習指導要領で検討されている「裁量的な時間(仮称)」の活用にも大きな期待を寄せています。
そもそも「インクルーシブってなんだろう?」─海外の制度をそのまま真似るのではなく、日本ならではの知恵や工夫を持ち寄り、これまでの「普通」を少しずつアップデートしていくことが必要だと感じています。そして、特別支援学校の先生方が、より多くの時間を子どもたちの学びに向き合えるよう、教育委員会をはじめとする関係機関のご理解とご協力を賜れたらと願っております。
今後も、子どもたちとその家族、そして教育現場で日々尽力されている教職員の皆さまの声が尊重され、誰もが安心して自分らしく学び、働き、暮らせる社会の実現を目指して、全国の皆さまと共に考え、手を取り合って進んでまいります。
本年度もどうぞよろしくお願い申し上げます。
令和7年7月4日